【プロ県議の現場主義 #3】新潟県民の「住」を取り巻くリアルな事情 <新潟県議会議員・市村浩二>
直近の記事を再掲載します
初回掲載:2025年9月21日
耐震シェルターのすすめ
2011年8月に内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の発足以来、わが国に近い将来起こりうる大震災への懸念が、近年さらに高まっている。
そんな中で、住宅の耐震性が最重要課題である。特に耐震仕様の乏しい古い住宅の問題は深刻だ。わが国では建物を建てる際、建築基準法によって耐震基準が定められている。建築基準法は昭和56年(1981年)に耐震基準が新しく定められ、同年5月以前に建築された建物が、いわゆる「旧耐震基準」の建物なのだが、その内容は「震度5程度の地震でも建物が崩壊せず、大きな損傷を受けないこと」という程度で、なんとも脆弱なのだ。かくして震度7の地震が2回も発生した2016年の熊本地震では、旧耐震基準で建てられた多くの家屋が全壊した。
これを考えると旧耐震基準で建てられた古い住宅は、安全性を考えれば耐震改修は喫緊の課題としなければならない。
全国の自治体で耐震診断や耐震改修促進のための補助事業に取り組んでいるが、新潟県でも「耐震すまいづくり支援事業」として、1981年5月以前に建築された古い住宅を対象に制度を設けている。新潟県の令和2年度末における住宅の耐震化率は85%。全国の都道府県を見渡すとちょうど中間くらいの順位だ。
新潟県議会の市村浩二県議に話を聞いた。市村氏は長岡技術科学大学工学部出身で国家資格「技術士」(総合技術監理部門、建設部門)を取得し、住まいの安全性に対しては知見も関心も高いことで知られる。

住宅全体の改修より経済負担が少ない耐震シェルター
「新潟県でも耐震診断に対する補助制度には取り組んでいます。令和元年から5年までの間で年平均で約200件の住宅が耐震診断を行ったうえで『改修が必要』とされたのですが、問題はその先です。耐震診断を受けたけど、その後に補助制度を活用して耐震改修に及んだ例は、約1割というわずか20件にとどまっているのです。理由は明らかで、旧耐震基準の住宅に住んでいるのは高齢者がほとんどなので、いくら補助を受けられると言っても資金に余力がない世帯がほとんどですから」(市村県議)
これは深刻化する都市部の空き家問題にも通じるのだが、住宅にわざわざ資金を投入して改修しようというケースは「後継者」あっての話になるケースが多い。しかし人が住んでいる以上は、地震に耐えられずに倒壊する危険性のある家に住み続けるわけにはいかない。

認知度の低さから、耐震シェルターに対する制度利用件数はごくわずかにとどまっている
「そこで注目されるのが『耐震シェルター』の存在です。これは家屋の一部に耐震補強を施し、地震があった際にそこに逃げ込むというものです。居間や寝室などに耐震構造のシェルタースペースを設け、地震による倒壊時でも命を守れる空間をつくるものですが、家屋全体を耐震改修するよりも経済負担も低く済むのです」(市村県議)
確かに、耐震シェルターなら費用もさほどかからずに地震の際の安全確保が可能になる。これに関しては現段階で国土交通省など国からの補助制度は見当たらず、主に全国の自治体が中心となって取り組んでいる。
市村県議は令和5年の6月定例会建設公安委員会で、新潟県の耐震化促進について質問し、耐震シェルターの話題にも及んでいる。
新潟県でも平成28年から、部分耐震改修・耐震シェルター設置等補助事業を掲げ、耐震シェルターについては12市町村が取り組んでいるとのことだが、この時点で設置例は3件しか上がっていなかった。
「これは明らかにPR不足と言えます。認知度が足りていない。民間のリフォームフェアや県の防災訓練などの機会を利用して、もっと周知すべきだと思います」(市村県議)
能登半島地震でますます家の安全性が注目される今一度、我が家の耐震改修に関して見直す時期となっている。使える制度は、知られていないが意外に多い。
「こむすび住宅」の在り方について
「住んでよし、訪れてよし」を目指す新潟県では、子育てしやすい住宅の普及促進に向け、こどもの事故防止や家族のふれあい等に配慮した空き家のリノベーションを行い、子育て世帯等に販売する買取再販事業者に対し補助を行う「にいがた安心こむすび住宅推進事業」を実施している。こむすび住宅には雪国型ZEH(ネットゼロエネルギー住宅)に対する上乗せ分を含めて上限350万円の補助金が交付される。これに対して県では約1億6,000万円の予算を見込んでいる。まずは50件の供給を当て込んでいるのだ。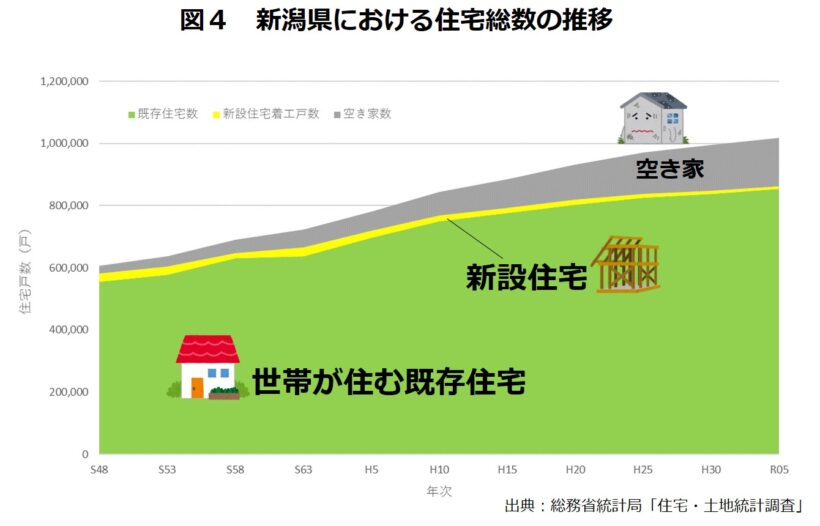
新潟県が抱える二つの課題、「人口減少・流出問題」「空き家問題」に対処すべく、花角英世知事の肝いりで進めている政策だが、狙いとしては子育て世代の県内定着、若い世代に手の届きやすい価格帯の住宅ニーズ対応、住宅再販事業への参入と既存住宅流通市場の活性化など多岐にわたる。
シンプルに言えば、社会問題となっている空き家を有効活用し、価格高騰で新築住宅に手が出せなくなった若い世代に向けて安価に住宅を提供して定住人口増につなげようという施策である。
これについて市村県議が、令和6年2月定例会連合委員会で質問に立ち、花角知事と議論を戦わせている。

令和6年2月定例会連合委員会でこむすび住宅のリスクマネジメントについて質す市村浩二県議
市村県議 補助額も大きいので、売買にかかわるリスクを踏まえた制度設計が必要なのではないか。本事業では補助金の投入先がこむすび住宅を購入する子育て世帯等ではなく、買取再販事業者であるため、売れ残った場合のリスクもある。もし売れ残れば、結果として本事業の狙いとする子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅購入者へ支援が届かず、補助金の活用、効果が発揮できないのではないか。制度の根幹をなす売買のリスク管理への県の関与も含め、売れ残った場合の対応に対する考えについて、知事の所見を伺いたい。
花角知事 子育て世帯等のニーズにこたえるリフォームであること、改修費の補助相当額を市場価格より値引きして販売することなどを要綱に定めている(よって恩恵を受けるのは購入者である子育て世帯だ)。また一定の期間を経過して売れ残った場合は、空き家利活用促進の観点から、販売対象世帯の要件緩和も検討している。

このやり取りに関して、市村県議はこう話す。
「私としても子育て支援、空き家対策、雪国型ZEHの促進という一石三鳥の政策には大いに期待をしたいところ。その一方で、販売については売れ残りリスクもはらみます。住宅の購入は一生に一度の買い物ですが、その時には住宅の性能や外観だけでは判断されることはありません。立地や利便性も重要な要素だと思います。エンドユーザーの住宅に対する要望を聞いてリフォームされたわけではないので、既存の建売住宅のように売れ残りリスクはどうしても生じるのではないでしょうか」

市村県議は今年2月の定例会一般質問でもこむすび住宅について質問している
買取再販事業者にとってはほとんどリスクのない制度だが、例えば売れ残った際に業者に対して「補助金を返還せよ」というのは言えないだろう。そうすれば参入する業者はほとんどいなくなるのが現実だ。
長期優良住宅やZEHなど、近年は住宅に関する補助制度も多様化してきたが、多くはエンドユーザーに直接交付される形がほとんどだ。行政としては住宅再販業界の活性化を促し、ひいては新潟の住宅流通を活発化させようというのが狙いかもしれないが、果たしてどう出るか。
令和6年度末時点の進捗では、こむすび住宅事業に登録を申請した事業者が70者、交付申請を行った物件は30件となり、既に予算から逆算する目標の半分以上に達している。完成した物件は3件で、うち既に1件には購入者が入居しているという。
【過去の記事】

