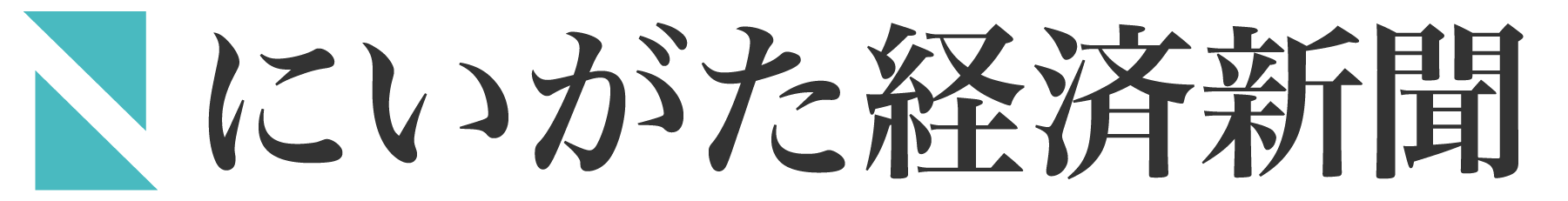【特集「健康経営」対談】健康経営で会社と社員がともに成長 ~株式会社おこめ商事の取り組み~
精米機器製造のリーディングカンパニーとして知られる株式会社おこめ商事。同社は5年前から本格的に健康経営に取り組み、社員の健康増進と企業価値の向上を両立させてきた。
今回は、同社の山田太郎社長と、健康経営コンサルティングを手掛ける株式会社アイセックの木村大地氏に、その取り組みの詳細や成果、今後の展望についてお話を伺った。
精米機器のリーディングカンパニーとして

山田:本日は、弊社の健康経営の取り組みについてお話しさせていただく機会をいただき、ありがとうございます。
木村:こちらこそ、おこめ商事様の先進的な取り組みについて、お話を伺えることを楽しみにしておりました。まずは、御社の概要についてお聞かせいただけますでしょうか。
山田:弊社は1975年の創業以来、精米機器の製造・販売を手掛けてまいりました。現在は従業員300名ほどの規模で、国内シェア35%を占めております。近年は海外展開も積極的に進めており、アジアを中心に事業を拡大しています。また、IoT技術を活用した次世代型精米機の開発にも注力しており、業界のデジタル化を牽引する存在として評価いただいています。
社員の健康危機が転換点に

木村:御社が健康経営に取り組もうと思われたきっかけについて、お聞かせください。
山田:きっかけは5年前、ある社員の過労による体調不良でした。当時、海外展開を進めていた最中で、社員の多くが長時間労働を余儀なくされていました。その社員の件をきっかけに、「会社の成長と社員の健康は、どちらも疎かにしてはいけない」と強く感じ、健康経営の導入を決意しました。
木村:導入に際して、社内での反応はいかがでしたか?
山田:最初は戸惑いの声もありました。特に管理職層からは「業績への影響を懸念する声」も上がりました。しかし、経営陣が強い意志を持って取り組む姿勢を示し、段階的に施策を導入していったことで、徐々に理解が広がっていきました。
3つの柱で推進する健康経営

木村:なるほど。具体的にはどのような取り組みを実施されているのでしょうか。
山田:大きく3つの柱を立てて進めています。1つ目は「働き方改革」です。残業時間の上限設定や有給休暇の取得促進、フレックスタイム制の導入などを行いました。特に力を入れているのが、業務の効率化です。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入や、会議時間の短縮、ペーパーレス化なども積極的に進めています。
2つ目は「健康増進施策」で、社員食堂でのヘルシーメニューの提供や、社内ジムの設置、健康セミナーの定期開催などを実施しています。また、歩数に応じてポイントが貯まるウォーキングアプリを導入し、運動習慣の定着を図っています。
3つ目は「メンタルヘルスケア」で、産業医との定期面談や、ストレスチェックの実施、カウンセリング制度の充実などに取り組んでいます。特に力を入れているのが、管理職向けのメンタルヘルス研修です。部下の心の不調に早期に気づき、適切な対応ができるよう、定期的にトレーニングを実施しています。

数字で見える、着実な成果
木村:包括的な取り組みをされていますね。これらの施策による具体的な効果はいかがでしょうか。
山田:まず数字で見える効果として、導入から3年で平均残業時間が月45時間から28時間に減少し、有給休暇取得率は52%から78%まで上昇しました。また、健康診断での要再検査率が35%から22%に低下するなど、社員の健康状態も改善傾向にあります。さらに、従業員満足度調査でも、「会社は従業員の健康に配慮している」という項目の評価が5段階中2.8から4.2に上昇しました。離職率も15%から8%に改善しています。
木村:業績面への影響はいかがでしょうか。
山田:当初懸念されていた業績への悪影響は全くありませんでした。むしろ、労働生産性が向上し、一人当たりの売上高は1.2倍に増加しています。また、「健康経営優良法人」の認定を取得したことで、企業イメージも向上し、新卒採用での応募者数が1.5倍に増加するという効果も出ています。
現場で見えてきた新たな課題
木村:素晴らしい成果ですね。一方で、課題に感じていることはありますか。
山田:はい。現在直面している課題は主に2点あります。1つは、部署による取り組みの温度差です。特に営業部門では、客先との関係で勤務時間の調整が難しく、改革が進みにくい状況です。もう1つは、中間管理職の負担増です。様々な施策を実行する中で、管理職の業務量が増加している実態があります。
木村:その課題に対して、具体的な対策は検討されていますか。
山田:はい。特に営業部門については、客先との商談のあり方自体を見直そうとしています。例えば、オンライン商談の活用を提案し、移動時間の削減を図るなど、お客様にもWin-Winとなる方法を模索しています。
「健康経営2.0」へのステップアップ
木村:なるほど。その課題に対して、今後どのように取り組んでいく予定でしょうか。
山田:まず、部署間の温度差については、デジタル技術を活用した業務効率化を進めていきます。具体的には、営業支援システムの導入やオンライン商談の促進などです。また、管理職の負担軽減については、専門チームの設置や外部リソースの活用を検討しています。
今年度からは「健康経営2.0」と銘打って、新たな取り組みも開始します。例えば、従業員の家族も参加できる健康イベントの開催や、健康増進に関する手当の新設などを計画しています。さらに、健康経営の取り組みを取引先にも広げていく予定です。
社会に貢献できる企業を目指して
木村:最後に、健康経営を通じて目指される会社の姿についてお聞かせください。
山田:私たちが目指しているのは、「社員が心身ともに健康で、いきいきと働ける会社」です。そして、それは単なるスローガンではありません。社員一人一人が健康であってこそ、持続的な企業成長が実現できると考えています。また、私たちの取り組みが、取引先や地域社会にも良い影響を与えられればと思っています。健康経営を通じて、社会に貢献できる企業でありたいと考えています。
木村:本日は貴重なお話をありがとうございました。御社の取り組みは、多くの企業の参考になると思います。今後のさらなる発展を楽しみにしています。
山田:ありがとうございました。まだまだ道半ばですが、社員とともに一歩一歩前進していきたいと思います。
健康経営がもたらす、新しい企業価値の創造
おこめ商事の事例は、健康経営が単なる社員の健康管理施策ではなく、企業価値を高める重要な経営戦略となりうることを示している。同社の取り組みの特徴は、経営トップの強いコミットメントのもと、デジタル技術も活用しながら、包括的かつ継続的な施策を展開している点だ。
また、健康経営の効果を、残業時間や有給取得率といった定量的な指標で測定し、PDCAサイクルを回している点も注目に値する。さらに、その効果が社員の健康状態の改善にとどまらず、生産性の向上や採用力の強化にまで及んでいることは、他社にとっても大きな示唆となるだろう。
働き方改革や健康経営への注目が高まる中、おこめ商事の挑戦は、企業が持続的に成長していくための新しいモデルケースとなりそうだ。
(文・撮影 中林憲司)