【若手が育つ企業】日本の鉄道インフラを守る松山重車輛工業「クリエイティビティの際立ち」

若手が生き生きと仕事をする工場の風景
厚生労働省が認定する「ユースエール認定企業」のひとつに松山重車輛工業株式会社(新潟市北区)が選ばれ、2025年3月には厚生労働省新潟労働局(新潟市中央区)で認定式が執り行われた。
ユースエール認定は、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度。
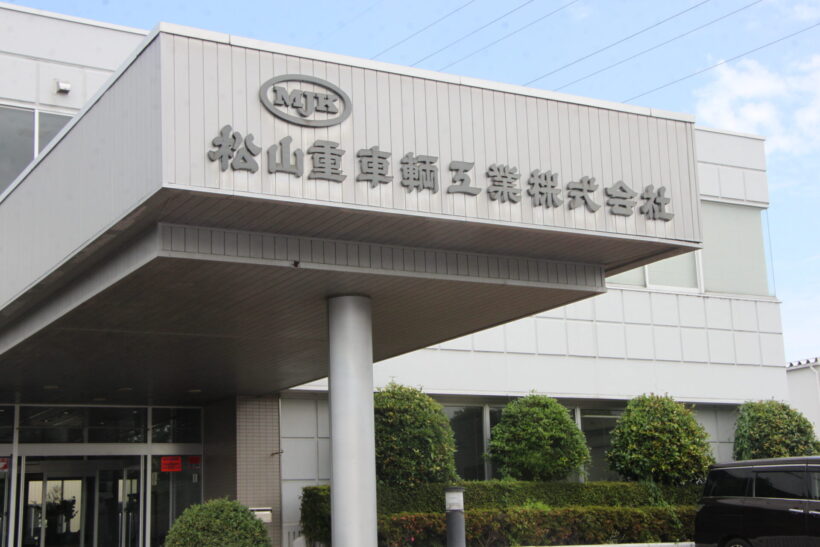
新潟市北区にある松山重車輛工業株式会社
鉄道インフラや大工場の敷地内などで活躍する軌道保守作業車のメーカーは数少なく、市場自体が大きくないこともあり、ほぼ国内5社で構成されている。そのうち3社が新潟市にあるというのは、ある種のトピックだ。昭和25年に創業した(前身の松山自動車工業は昭和15年創業)松山重車輛工業は、軌道モーターカーの部門において国内随一のメーカーであり、現在もJRを含めてほぼ国内の私鉄すべてが取引先となっている。
鉄道作業車自体、我々が普段はあまり目にしない存在ということもあり、新潟にこのような高い技術力と雄弁に語る歴史を持つ企業が存在すること自体、あまり知られていない。

製缶から細かい部品まで、内製化できる技術力がある
企業を存続させるものは、収益面の業績ばかりではない。常に次世代の会社を担う存在が育っていく環境が作られ続けなければならない。ユースエール認定を受けた同社の社員平均年齢は36.3歳。製造業の中で若く、定着率も高い。若手が育つ風土を企業が有している、と言ってもよい。
松山憲雄代表取締役に話を聞いた。

「線路が続く限り、この仕事はなくならないと思っている」と松山憲雄社長
全てを内製化できる高度な「設計力」
― 鉄道作業車両のメーカーは、現在国内に5社程度しかありませんが、そのうち新潟に3社が集まっています。市場自体はシュリンクすることなく推移していますが、大手による寡占化もなく、中小企業が淘汰されることもない。どんな特異性があるのでしょうか
松山社長 どうでしょうかね(笑)。大手にとってはそんなにスケールメリットがある市場ではないということなのでしょうね。(取引先は)それぞれ求めるものも違うし、それに対応しなければいけない。同じものを何千体も作るのであれば、彼らも進出するのでしょうが。作業車なので、ただ走る、曳くだけでなく様々な機能が付くわけですから、試作、試作の連続で。
― そうした業界にあって御社の強みは?
松山社長 うちは従業員70人の中に設計担当者が15人ほどいて、これほど設計技術者が充実している会社もないと思います。同じ製品をいくつも製造することはなく、ベースがあってそれをアレンジしたり、ゼロからオーダーメイドの車両を作ることもあります。その都度、設計者がアレンジして引き直して。それに対応していける体制であるということです。
主要部品であるディーゼルエンジンやトランスミッションはさすがに外部調達ですが、他社が外注しているような部品などについても、自社で設計し内製化できる技術と設備があるので、そこは自慢できる点だと思います。どうしても効率、コストの面で分が悪いところはありますが、その向こうに何万の人の安全確保があるわけですからね。

― 海外展開や新エネルギー対応機種の開発など、今後の松山重車輛工業の展望は
松山社長 海外戦略にも取り組んでいきたい気持ちはあり、実際に引き合いもあります。日本の鉄道を海外に売っている中で、パッケージの一部分として保守作業車両もということですが、アフターフォローを考えると現実化しないのですよ。ウチのようなメーカーは納品して終わりではないので。
一方で、環境規制への対応として、電気やハイブリッド、いずれは水素への移行は考えていかなければいけないでしょうね。試作は進めています。
この仕事は、線路が続く限り存在すると思っているし、技術力やノウハウに対する信頼性も築き上げてきたつもりです。

高い定着力、やりがい
― 3月にユースエール認定を受けましたが、若手の定着率が非常に高いですね。昨今は日本の社会もかつての終身雇用の概念が薄れ、自分のキャリアアップに乗じて次々に働くステージを変えていく人も多く、優秀な若手を定着させるのはどの会社も苦労しています。若い人がやりがいを持って仕事ができる環境づくりの秘訣を教えてください
松山社長 難しい質問です。休みとか就業時間に対しての考え方は、私たちが若いころとは常識が変わっていますからね(笑)
うちは、小さいながらもゼロからはじめて完成品まで作り上げて納品するという、ものづくりのすべてに関わっていく現場というのは、やりがいを感じてもらっているとは思います。
組み立てが終わって、電気の配線をして、そこでようやくエンジンを回す。これを私たちは「火入れ」というのですが、エンジンが音を立てて動き出した時の達成感は他では代えがたいものがあります。こうした喜びは、やりがいだと思いますよ。自分で絵を描いたものが形になる、組み立てたものが動き出す。その先にお客様の喜びがある。
毎日同じ仕事をするわけではないので、それだけ大変ですが、面白みはあると思いますね。皆、ものづくりが好きな子ばかりだと思いますので。

モノ作りが好きな若い人が、やりがいを持って働ける職場
― 採用の際に「こんな人が欲しい」という社長なりの基準はあるのですか
松山社長 基本的には「来る人は拒まず」と思っているのですよ。せっかく選んで来てくれたわけだから、なんとか良いところを伸ばしてあげたい、と。
