【企業ドラマ、かくも豊饒なり】 ベストプラクティス企業となった新潟電子工業、圧巻のファンタジー<完全版ディレクターズカット>

岡﨑淳新潟電子工業株式会社代表取締役社長
シャープに「捨てられた」子会社
新潟市南区にある新潟電子工業株式会社はエレクトロニクス系の製造業である。2025年には「働き方改革」への取り組みが評価され、厚生労働省から「ベストプラクティス企業」に選定されている。
これまで数多くの企業レポートを綴ってきたにいがた経済新聞だが、新潟県内においてこの会社ほど豊饒なドラマを背景に持った企業を、記者は知らない。ここまで辿ってきた激動の運命は、さながら「池井戸小説」で描かれる世界のようだ。
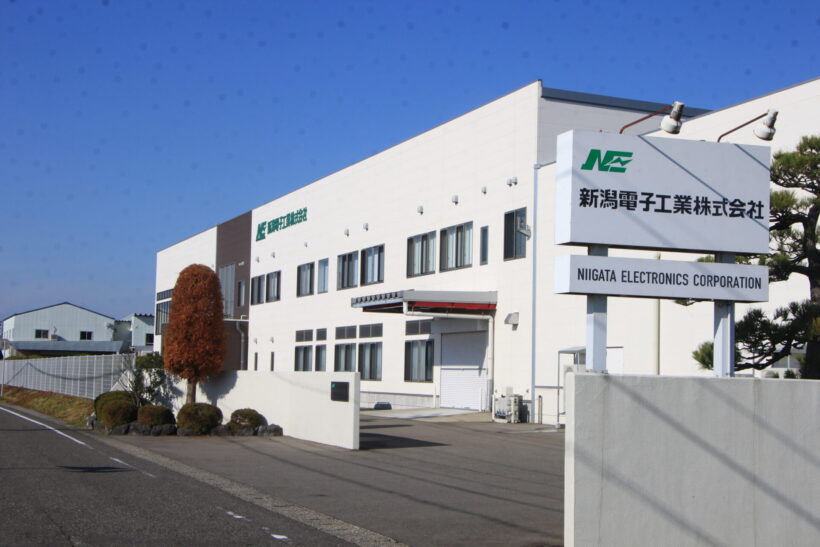
激動の歴史をたどった新潟電子工業株式会社(新潟市南区)
1970年に会社が設立。大手電機メーカー・シャープ株式会社と理研電線株式会社との合弁会社シャープリケン株式会社として生まれた。シャープが開発した当時最先端とも言える電卓の組立工場と言う役割だった。
同社は1976年にシャープの完全子会社となり、1987年にはシャープ新潟電子工業株式会社と屋号も変えた。やがて電卓市場が大量生産から価格競争の波にさらされると、生産子会社である同社は苦境脱却にさらされる。そこで親会社への一極依存から脱しようと独自技術の開発に至る。それがスイッチング電源の開発だった。
子会社ながらも築かれた技術開発型の土壌は、やがてミレニアムを迎えて効いてくる。「亀山ブランド」のシャープが世界に名をはせた液晶。これを支えたのは新潟だった。2001年には液晶バックライトの開発が始まり、同時に開発された蛍光管用インバーターがシャープの液晶テレビに採用された。シャープ亀山工場で生産される液晶テレビの電源とインバーターは、何を隠そうシャープ新潟電子工業の生産だった。2009年にシャープは、4,300億円をかけて大阪府堺市に液晶パネル工場を建設。「液晶のシャープ」の栄華とともに、この分野への極端な振り切りがリスク含みとさえ囁かれた。
親会社の破竹の勢いとともに、シャープ新潟電子工業の売り上げは2010年に約250億円に達し、過去最高を記録した。しかしその翌年、それまで右肩上がりを続けていた売り上げは、およそ3分の1の84億円に大幅下落する。コモディティ化した液晶テレビ市場は価格競争が激烈化し、海外に生産拠点を求め始めた親会社からの発注がピタリと止まった。またもう一つの柱だった富山工場生産していたソーラー向けシリコンウエハーも、わずかにあった電子部品の受注もほぼゼロになった。
これまで「世界の亀山モデル」を支えた子会社は、非常にもシャープに「捨てられた」のだ。2012年には52億円まで減らし、売り上げは2 期前の約5分の1になった。普通なら現実的な倒産危機水域である。
2011年10月に広島県のシャープ三原工場から赴任した岡﨑淳社長(現新潟電子工業株式会社代表取締役社長)は、焼け野原に降り立った気持ちに違いなかっただろう。「シャープの社員時代に反抗的だったので、子会社に飛ばされたのですよ(笑)」(岡﨑社長)

自社製品で盛り返すも、売却寸前に
岡﨑社長にも意地があった。何より、親会社の都合に翻弄され会社が窮地に立たされた中でも真面目に仕事をする社員たちの姿を見て「このまま終わらせてたまるか」という気持ちがふつふつとわいた。
「最初は『土下座外交』ですよ。亀山(三重県)、広島、栃木などシャープの全国各地の生産拠点を回って『仕事出してください』と。生産子会社ですから営業担当も二人くらいしかいなかった。ところがやはり、うちが液晶テレビで『切られた』ことをわかっているから、仕事が出ませんでした」(岡﨑社長)
そこで岡﨑社長はあらためて自社の姿に立ち返った。シャープ製品の生産工場としてほぼ1本足打法で来たが、コア技術シャープが持っていないパワー系(ソーラーパワーコンディショナーなど)やLEDの技術を持っていた。いずれも海外製品の質が国内製品に遠く及ばない分野だった。これでシャープへの依存体質から脱却できると確信した。営業グループを再編し、岡﨑社長も先頭に立って自社製品の営業に奔走した。その結果、2013年の売り上げは少し持ち直して72億円。それでも売り上げはシャープ子会社の中で最下位だったが、2014年にはついに単年度黒字へと転じた。
一方でシャープ本体は業績悪化の一途をたどった。「売れるものは何でも売って延命を図る」そういう段階に来ていた。新潟の子会社が、そのターゲットになるのは自明の理だった。2015年、自社製品の営業で活路を見出し、再度黒字浮上したこの会社に、あるファンドが目を付けた。

2025年に竣工した新工場のジオラマが展示される
MBOという選択肢
岡﨑社長は「ファンドが買いたがっている」という話を、当時シャープの常務取締役から聞いた。常務はシャープの生え抜き社員ではなく、銀行から出向で来ていた人だった。銀行マンとしてベンチャー企業育成などを手掛けてきた常務は、小規模ながら自社案件で奮闘する地方の子会社に何かと目をかけてくれたという。
「普通は、子会社の雇われ社長などには売却話など知らされないものです。売却された後に新聞で知るのが関の山で。本社から呼び出しがかかり『お前らで会社を買え。お前が社長を続けろ』と言われました。『3日待ってください』と言い残して新潟に戻り、早川守専務ほか役員に相談したところ『我々で買いましょう。我々もお金を預けますから』と賛同してくれました」(岡﨑社長)。早川専務もまた、下請け仕事への依存体質に忸怩たる思いを抱いていた一人だった。
経営陣によるMBO(自社買収)に向けて金策が始まった。本社の常務は「お前らで買え」と尻を叩いてくれたものの、当然だがファンドの提示額は教えてくれない。MBOを成功させるにはファンドの提示額を上回る額を集めることが必要だった。
当初は、金融機関も渋い顔だった。銀行からは当初「融資できるのは2億円が限度」と言われた。ファンドがいくら提示しているかは不明だが、2億円ではとても上回ることができないのはわかっていた。しかし味方になってくれる経営者のとりなしや粘り強い交渉により、融資限度額は次第に引きあがっていく。2億円が4億円、8億円と引き上げられ、最終的に11億円の回答を引き出すに至った。これに、役員が持ち寄った全財産1億円を合わせ、岡﨑社長らは計12億円で勝負に出た。
MBOは成就し、100%自社買収によってシャープとの合意にこぎつけた。岡﨑社長ら経営陣が金策に奔走し始めてから約3か月後のこと。2015年のカレンダーは12月になっていた。12月22日、東京証券取引所を通じて一般公示されると、社長は全社員を食堂に集めて言った。
「これからは自分たちだけで、力を合わせてやっていこう」。
この3カ月間、MBOの流れを知っていたのは5人の役員だけ。社員には一切知らせていなかった。社員の反応はそれぞれで、新たな船出を喜ぶ者もいれば不安そうな顔をする者もいた。
その日からたった5日後の2015年12月27日、衝撃が走った。
台湾の鴻海精密工業がシャープを3,888億円で買収するというニュースの入電。こんな運命のいたずらが時として起こる。事実上「消えた」のは親会社の方で、生産子会社だった新潟の工場は新潟の「地場産業」として生き残った。「もし」その手前でMBOが成立していなければ現在の新潟電子工業はどうなっていただろうか、と考えずにはいられない。
大胆な経営改革「20億でやっていける会社」に
新しい会社をどうしていこうか。岡﨑社長がまず掲げたのは「ガラス張りの経営」だった。大手のメーカーは、とかく経営陣と一般社員との距離の隔たりが大きい。社員は会社の経営や財務状況が現状でどうなっているのかを知らされていない場合がほとんどだ。これについては功罪合い半ばなのだろうが、新潟シャープ電子工業は既にシャープと言う大企業の傘を脱し、地方の中堅企業になっている。月一回開かれる全体朝礼で当月、半期の見込みの情報がシェアされ、半年に一度の方針説明会で業務実績と課題、対策が共有された。方針説明会の後には決まって飲み会を開いて、会社に一体感が生まれた。
「会社が大変だった2011年から2014年頃までは、私自身も社員に対して厳しく接していたところもありました。こちらも必死だった分『(売り上げが足りない)それならどうするんだ、どう頑張るんだ』と。シャープ時代の名残ですよね。昭和の大手メーカーは、どこもそういうノリがあったのではないかと思います。しかしこれからは、それではいけないと考えました。無理なものはどうやたって無理なのですから(笑)」。シャープ子会社時代にあった「昭和のモーレツな風潮」を払しょくすることから始めた。
事業は、会社のコア技術であるアナログ電源を柱にしながら、省エネ分野で光ダイオード(LED)照明を中心とするODM(相手先ブランドによる設計・生産)に注力していく方針が定められた。
2018年には社名をそれまでの「シャープ新潟電子工業」から「新潟電子工業株式会社」に変更した。

2017年から取り組んでいる受注・生産のDXは働く環境の効率化を実現した
ノルマなし、子育てしやすい職場に
前述のように独立してからの同社は労働環境が改革され、シャープ時代の「働け働け」というモーレツ社風は消えている。象徴的なのは、生産分野でも営業分野でも「ノルマ」の概念を止めたことだ。
「168人の小さな会社ですから『どこにどれだけ売れるか』なんて生産計画の段階で見えているわけですよ。いくら『何とかしろ』と言ったところで無理なものは無理。2017年から2024年まで目標値に達した年などありませんから(笑)」(岡﨑社長)
以前は多かった会議も極力減らした。2012年に月30回程度で22時間費やされた会議は、2024年に月8回程度で7時間のみとなった。会議の目的を再確認し、あり方を見直した結果だ。
2017年には受注から生産まで一貫したDX化への取り組みに着手。受注と連動して自動的に部材が発注され、生産・技術分野の資料はデータに一元化された。こうした取り組みが「ノルマなし経営」実現の一助となっている。
働きやすく、子育てしやすい労働環境の実現にも取り組んだ。残業時間は大いにカットされ、定時で退勤しやすい社内環境を整えた。育児休暇制度を設け、2020年以降の育児休暇取得率は男女ともに100%。企業風土としての「働きやすさ」「育児しやすさ」が刷り込まれてきた。男性でもしっかり育休を取るし、育児休暇後にも職場復帰しやすい環境が用意されている。有給休暇は1時間単位で取得できる。「子供が急に発熱した」「急に送り迎えが必要となった」など子育てではありふれたシチュエーションだ。同社では毎年平均で5人の出産がある。国が定めた水準の約5倍に相当するのだそう。
こうした取り組みが評価され、冒頭に示した通り、厚生労働省による2025年に「ベストプラクティス企業」(長時間労働削減や柔軟な働き方に積極的に取り組む、各都道府県労働局が選定した企業)に選定されている。厚労省のユースエール企業(若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業)にも5年連続、6度の選定。くるみん(厚労省が認定する「子育て支援企業」)にも選ばれた。
「自分で自分のところの会社を褒めても説得力がないので、こうした『錦の御旗』は大変ありがたい」と岡﨑社長は控えめに話す。
新潟のひとつ企業が辿った数奇な運命は、我々に何を示すのか。禍福はあざなえる縄のごとし。こうした闘争の日々を経て、今や「働きたい職場」として称賛される会社が、新潟にあることを覚えたい。
(文・写真 編集部 伊藤直樹)
